こんにちは、やまじです。
今回は自分で作成したライフプランのお話です。
30後半になり、子供もできると色々考えることがでてきます。
その中でも今回は”お金”について書きたいと思います。
正直、今生活が苦しいといわけではないのですが、漠然とした不安が出てきます。
子供の教育費は足りるのか 老後は大丈夫だろうか 自分に万が一のことがあったら・・・ などなど
そんな時、保険に加入する時に保険会社の担当者とライフプランを作成したのを思い出しました。
加入当時とは状況も変わっているので、自分で作成してみようと試みました。
ざっくりとでも先が見通せれば、不安が和らぐのではないかと考えたからです。
ちなみに金融知識も持ち合わせていない素人が作成しているので、かなり抜けが多いと思います笑
実際の金額は記載できませんが、考え方などが参考になればと思います。
ライフプラン作成にあたって
・家族構成
今後の家族構成を考えました。今は妻と子供一人。このままいく可能性もありますが、もう一人くらい増える想定で進めていこうと思います。
・ライフイベント
人生の3大支出のうち、「住宅」については購入するつもりは一切ないので、代わりに「車」を入れた、
「教育」「車」「老後」を考えていきます。
支出
①教育費
まずは不安の一つでもある教育資金を確保するために、どれくらい教育資金がかかるものなのか実際に金額に調べてみました。
進路としては保育園(2人目)、小学校から高校まで公立、大学は私立文系を想定。
教育費の試算については下記を参考にしました。
・保育料は1人目で実際に支払った金額
・高校までは文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」
・大学は文部科学省「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
②車関係
車が必須な地域ではないですが、あれば便利ですし、運転も割と好きなので、定期的な車両購入をしていきます。
4回目の車検で乗り換えるとして、9年毎に買い替えとします。
③老後
特に大きな支出はないですが、65歳で退職として、年金がいくらくらいもらえるか確認。
④生活費
生活費は日々の家計簿から算出しました。
これで支出関連の洗い出しが終わりました。
続きまして収入関連を見ていきましょう。
収入・貯蓄
①給与収入・・今の会社で65歳まで勤め上げたとして、例年の定期昇給で算出
(あまり出世欲がないので、昇格を想定しませんでした・・・笑)
②貯蓄・・今の貯金・投資額で継続した場合で算出
投資額は評価額を考慮せず、積立の金額で算出しています。(上がるか下がるか分からないので)
③年金・・65歳まで勤めたとして、年金機構の計算方法を参考に試算
国民年金・・・令和6年4月分の満額は月額68,000円✖️12ヶ月=816,000円
※日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
厚生年金・・・平均標準報酬額✖️0.005481✖️平成15年4月以降の加入期間の月数
(年金制度が難しすぎたので、報酬比例部分?というところだけ見ています)
※日本年金機構「は行 報酬比例部分」
確定拠出年金・・会社の退職金制度であり、毎年の掛金を増加させて算出
以上が収入関連になります。
死亡時に入金になるもの
私自身に万が一の事態があった時に家族にどれだけのものが残せるのか確認していきます。
①保険金・・民間保険と都民共済に加入しています。加入内容としては収入保険と死亡一時金です。保険会社からもらった試算表を確認。
②遺族年金・・年金機構によると、厚生年金の報酬比例部分の4分の3らしいです。
③確定拠出年金 死亡時に一括で支払われるので、死亡時点の残高としました。
確認事項
概ねお金に関する事項を棚卸しできました。
ここからは自分が生存した場合と死亡した場合で黒字になっているか確認。
・生存時
(毎年の収入+貯蓄)ー(毎年のライフイベント+毎年の生活費)
毎年黒字になっていればOK
・死亡時
(死亡時点の貯蓄額+死亡時点の確定拠出年金の金額+死亡保険)ー(全期間の教育費用の合計金額)
黒字になっていればOK
子供の教育資金は確保できました。また、車については妻は運転できないので、除外しています。
(遺族年金+収入保険)ー(毎年の生活費)
こちらについては毎年が黒字、もしくは大きく赤字になっていなければOK
まとめ
子供1人もしくは2人、私に万が一のことがあっても黒字になっていました。
ただ最初にもお伝えしたとおり、素人が作成しているので、もっと検討した方がいいところがあります。
例えば・・・
高校まで公立としましたが、私立に行きたいとなるかもしれません
生活費も現状維持としていましたが、子供が大きくなると少なからず上昇しますし、インフレも考慮していません
逆に妻の収入や貯蓄額は一切含んでいないので、世帯としてみればもう少し余裕があるはず・・・などなど
今回ざっくりと調査方法で作成しましたが、当初の目的である将来のお金の不安を和らげるという点では、十分な結果が得られました。
まだまだ検討余地があるので、今後も定期的な見直しを図っていこうと思います。
ご自分で作成しようと考えている方に、少しでも参考になれば幸いです。
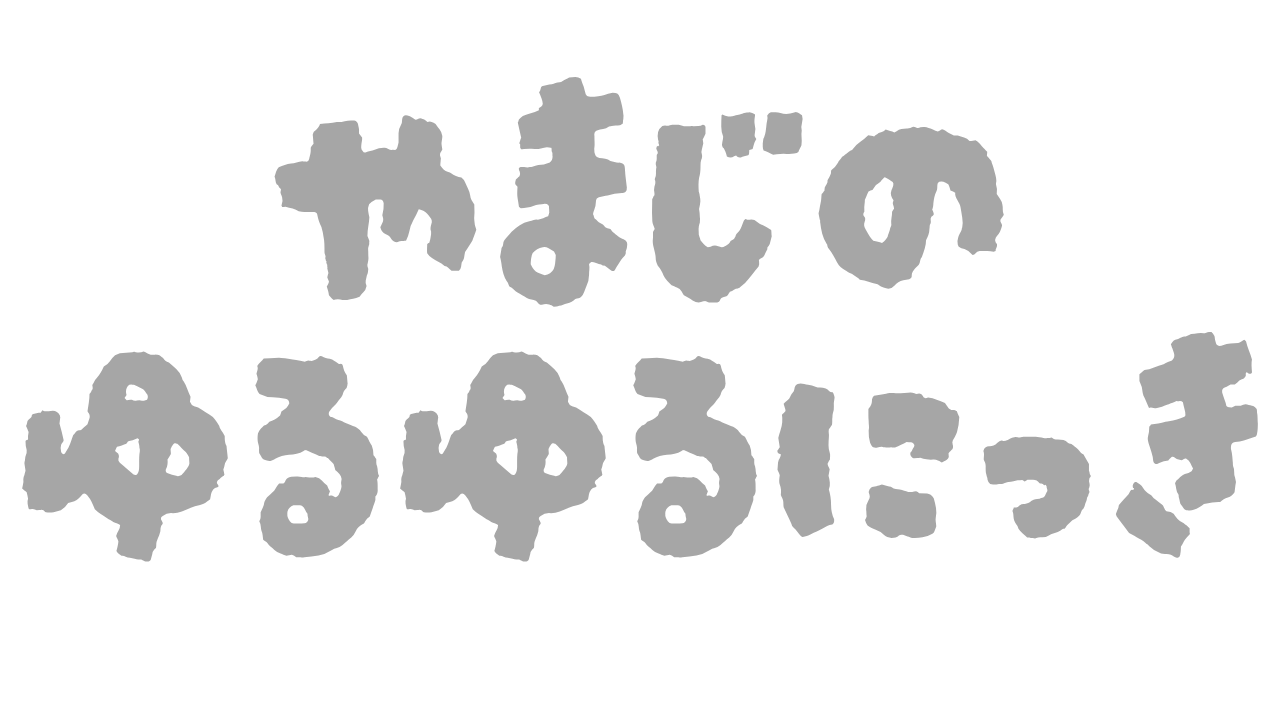


コメント